多くの人は「何をするか?」や「何を選ぶか?」という、「何か(=What)」をすごく気にします。
行動や選択の「対象」を気にしているという事ですね。
- そんなことやって、なにか役に立つのか?
- そんなことやっても意味がないぞ
- そんなことよりこっちをやった方が将来役に立つよ。
- 今の時代、流行は〇〇だ
このように行動や選択の「対象」ばかりに目が行く人が多いです。そして、それは、教育や子育ての場面でも多く当てはまります。
- なんでそんなことしたのよ?!
- 〇〇よりも△△のほうが良いんじゃない?!
親としては、なんとなく言っている一言が、子どもにとっては大きな影響を持つ言葉だったり、子どもの一生に影響する言葉になる可能性だって大いにあります。
注目すべき点は、選択の「対象」ではなく、選択という「行為」そのものなのです。
以前の記事でも、人間の幸福感に大きく影響するのは、自己決定要素であると明らかになってきています。誰かが決めたことをやるのではなく、自分が決めたことをやる、ということが大事だということですね。
自己決定の重要性では、こんな研究もあるようです。
どんなオフィス環境で仕事をすれば、生産性が上がるか?という実験を行いました。以下の3つのデスク環境を作って、実験したそうです。
- 会社が決めた画一的で無機質なデスク環境
- 植物や絵画を飾ったデスク環境
- 自分が好きなように創ったデスク環境
結果は、皆さんのご想像の通り、3番の自分が好きなように創ったデスク環境だったそうです。興味深いのは、好きなように創ったデスク環境が、結果的に「無機質なデスク環境」や「植物と絵画を飾ったデスク環境」だったとしても、1や2の環境よりも生産性が上がったという点です。これは非常に興味深い結果ですね。何を選ぶかではなく、「自分で選ぶ」という行為そのものが重要である事がわかります。
教育や子育てにおいては、親や先生など「大人の保育者の前提」をもとに、一方的な教育がなされがちです。
まだ人生経験の乏しい子どもの判断力は、大人の判断力よりも劣っている。
多くの大人はそのように考えているのではないでしょうか。
しかし、果たしてそうでしょうか?
本当に子どもの判断力は劣っているのでしょうか?
重要なことは、判断力の良し悪しや、何を判断するかではなく、「自分で判断する」という行為そのものです。親の一方的な押し付けにより、大切な大切な「子どもが自分で判断する機会」を奪っていることがたくさんあるのです。
何を選択するか?何を判断するか? よりも、選択したり判断したりする「行為そのもの」が非常に重要である点を肝に銘じたいですね。

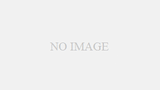

コメント