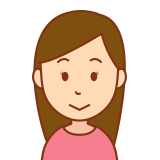
最近、幼児教育における非認知能力の育成が重要って聞くけど、日本ではどのような幼児教育がなされているのかな?
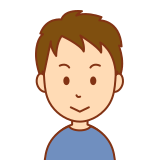
文部科学省が、非認知能力についてどのように考えているのか、丁寧に見ていこう!
非認知能力とは? 【簡単におさらい!】
非認知能力(スキル)とは、
意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、
なかなか測定できない個人の特性による能力のこと全般を指します。
いわゆる「学力(=認知能力)」と対照的に用いられる言葉です。
最近、世界の教育トレンドで、この非認知能力が注目を浴びています。
詳しくは、こちら → 【非認知能力とは?】世界が注目する能力を徹底解説
文部科学省がかかげる幼児教育の3本柱
文部科学省は、幼児教育における「3つの柱」を提示しています。
- 個別の知識や技能の基礎
遊びや生活の中で、豊かな体験を通じて、何を感じたり、何に気付いたり、何がわかったり、何ができるようになるのか - 思考力・判断力・表現力等の基礎
遊びや生活の中で、気付いたこと、できるようになったことなども使いながら、どう考えたり、試したり、工夫したり、表現したりするか - 学びに向かう力、人間性等
心情、意欲、態度が育つ中で、いかによりよい生活を営むか
文部科学省における非認知能力の定義
文部科学省が提唱する3つの柱のうち、「学びに向かう力、人間性等」が非認知能力に当たると考えられます。
「知識及び技能の基礎」や「思考力,判断力,表現力等の基礎」などの、いわゆる「学力(=認知能力)」だけではなく、非認知能力の重要性もしっかり盛り込んでいます。
文部科学省が考える「幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿」
さらに、文部科学省は、3つの柱のもと、幼児期の終わり、すなわち小学校入学までに育んでほしい姿や能力の目安として「10の姿」を提示しています。
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活と関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 量・図形、文字等への関心・感覚
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
これらを見てみると、教育トレンドである非認知能力の要素が含まれています。自立心と協同性などですね。
非認知能力を「良きものだ!」と捉えて、それを中心にゴリゴリと推し進めるのではなく、過去の日本の教育方針を良くも悪くも踏襲しつつ、昨今の教育トレンドも盛り込んでいる、という印象でしょうか。
文部科学省が推奨する「5歳児教育プログラム」
2021年7月、文部科学省が新たに5歳児教育の共通プログラムの開発を進めることを決めました。
文科省は8日、中央教育審議会の初等中等教育分科会を開き、5歳児教育の共通プログラムの開発を始めることを決めた。幼稚園、保育園、認定こども園といった施設類型にかかわらず「ことばの力」など共通に育てたい力を養い、小学校教育への円滑な接続を目指す。近く特別委員会を設け、検討を始める。
幼稚園教育要領などでは、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として「健康な心と体」や「自立心」「協同性」など10項目を示している。共通プログラムでは、これを踏まえながらも、特に「ことばの力」「情報を活用する力」「探究心」を確実に付けさせるための方法を検討する。
同日の分科会では、就学前と小学校の教育をつなぐための議論に期待する意見が出る一方、「質的に違う教育をつなげるのは難しく、相互の理解が必要になるが、まだそれぞれの教育内容への理解が進んでいない。議論が上滑りする恐れもある」といった指摘も上がった。
文科省は特別委員会で年度内にプログラムの試案をまとめ、来年度からモデル事業として始める。特別委員会の委員には、無藤隆・白梅学園大学名誉教授や秋田喜代美・学習院大学教授が就く予定。
萩生田光一文科相は、5月に経済財政諮問会議で公表した「幼児教育スタートプラン」の中に「幼保小の架け橋プログラム」を明記。その後の会見で「ことばの力、情報を活用する力、探究心といった生活・学習基盤を全ての5歳児に保障する」と狙いを話していた。
初等中等教育分科会では、教育委員会事務局の機能強化を検討する有識者会議の設置も決めた。事務局職員の育成や校長を中心とした自律的な学校運営を支援するための教委組織について検討する。
学校運営の専門人材を育てるための特定のキャリアパスの在り方も議題にする。平成27年施行の改正地方教育行政法で設置を義務付けた総合教育会議の活用についても議論される見通しだ。
日本教育新聞 2021年7月19日記事より
ポイントとしては、「幼児教育と小学校教育をつなげる」というところですね。
今までは、幼稚園や保育園での教育レベルの差があったり、あるいは、そもそもそういったところに子どもを通わせられなかったり、という家庭がありました。その結果として、いわゆる「小1問題」と呼ばれる、小学校に入学した時点で、子どもの学習レベルに差が生じる問題がありました。
それを防ぐために、文部科学省が国の施策として小学校就学前に共通の教育プログラムを用意しようというわけですね。
また、幼児教育・保育の無償化も、同じ問題が背景にあります。経済面を理由に、幼児期の教育に差が生じないように、幼児教育・保育が無償化されました。
文部科学大臣の幼児教育に対するコメント(2021年7月)
上で述べたとおり、文部科学省は新たに5歳児教育の共通プログラムの開発を決めたわけですが、その後、文部科学大臣の記者会見コメントを残しています。
先週、中央教育審議会の初等中等教育分科会に設置をされた「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」では、地域や家庭の環境に関わらず、全ての子供が格差なく質の高い学びへ接続できるよう、学びや生活の基盤を保障するための方策などについて検討していただく予定です。現行の幼稚園教育要領や保育園の保育指針等では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の明確化など、学校種や施設の類型を越えて子供の成長を支える手がかりが共通に整理されています。これを踏まえ、現在既に、幼児期の教育と小学校教育双方の関係者の協力によって教育の充実を図る取組が進められているところですが、特に幼児期の教育に関しては、どのように教育の質をどう高めるかがイメージしにくく、接続期のカリキュラムの参考になる資料が少ないとの声があるところです。このため、特別委員会においては、五感を通じて学ぶ時期である幼児期の特性を踏まえ、こうした声に応えるためご議論をいただくことに期待をしているものであり、ご心配のようなですね、画一的な内容を求めたりするものではなく、子供一人一人の体験の幅を広げ、質を高めるため、各園の創意工夫が最大限発揮される内容となるような議論をお願いしたいと考えておりまして。この前、私、これ発表したときにも申し上げたように、全てを幼稚園化しようとかですね、幼児教育の指導要領を保育園にもはめ込もうとかそんなこと考えてるわけじゃ全くなくて、それぞれ個性あるいろんな子供たちの学びや遊びがあると思うのですけれど、その中で、小学校入学とのスムーズな移行ができるように、この部分だけは5歳児やっときましょうねっていう、いくつかのものを取り出してですね、それをまた上手に、保育園や幼稚園や認定こども園や、あるいは無認可保育園やあるいは保育園に行ってないお子さんたちもいらっしゃるわけですから、ご家庭でもそこに触れてもらえるようなものを何か作っていこうということなので。やや義務教育の前倒しみたいなことをおっしゃる方がいるんですけど、そんな迫力じゃなくてですね、本当に1年間、もっと言えば1日のうちのほんのわずかなことで、こういったことは、5歳児になったらできるようにしようねとか知っておこうねっていうようなことをしっかり身に着けてもらうことが大事だと思っていますので、イメージとしては、そういうことをしっかり話し合いをしてもらいたいと思っています。小学校入学後に果たすべき義務教育の役割は変わらないと思っていますので、そこはそこで、充実を図っていきたいと思います。
萩生田光一文部科学大臣記者会見録(令和3年7月16日)
義務教育の前倒し、いわゆる「お勉強」の前倒しではなく、幼稚園・保育所や家庭でもできる教育プログラムを確立していこう、ということを述べられています。
今後、新たに設立された「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」 で、具体的な教育プログラムの開発、議論を進めていくことになるのでしょう。今後の議論には、注目したいところですね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
昨今の世界の教育トレンドである幼児教育の重要性、非認知能力の重要性を踏まえつつ、日本独自の幼児教育スタイルを確立していこうとしている最中ですね。
5歳児教育の共通プログラムの開発は、個人的にも興味があり、引き続き注視したいと思います。文部科学省の中の「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」の動きには注目したいと思います。



コメント