4歳になる私の子供は、机に向かって簡単なドリルをします。
その様子を観察していると、集中力が持続する時もあれば、持続しない時もあります。これは非常に興味深いことで、私自身も研究対象として4歳の子供の行動やリアクションをよく観察しています。
【4歳児】集中力が持続するとき
ドリルの前に、楽しい時間を過ごしているとき。
兄弟と遊んでいたり、好きなおもちゃで遊んでいたり、とても楽しく過ごしたあとに、ドリルをすると比較的集中力が継続します。これは脳神経科学的にいうと、ドーパミンが放出され集中力が高まっているのかもしれません。
【4歳児】集中力が持続しないとき
寝る直前。
夜遅くにドリルをすると、だいたい集中力が持続しません。これは明らかに「眠たいから」ですね。親としてはドリルをさせる時間帯をうまく調整すべきだなと感じます。
【そもそもの問い】ドリルをさせることは良いことなのか?
自分も含めて、親はなるべく自分の子供に勉強を好きになって欲しいと思うものです。
非認知能力が重要だと言われている最近ですが、「そうは言っても、受験などのイベントをうまくクリアしてほしい」と思うのが親心であり、少なからず認知能力の向上というのを期待してしまいます。
では、認知能力の向上を、就学前の小さな子供達に強制して良いのでしょうか?
親としては、この問いにしっかり向き合わないといけません。
親は、仮に子どもがドリルに集中していなかった場合、ドリルに集中していない子供を叱責するのではなく、
- なぜ集中力が持続しないのか
- なぜ興味を示さないのか
- どうすれば興味を持って主体的に学習に取り組むようになるのか
こういったことを考えながら、子供の様子を観察することが非常に大事だと思います。
私も、日々、父親として子供の行動を観察して、どのようなアプローチが子どもにとって有効なのか試行錯誤しています。
子育てに関する情報をアップデートすることの重要性
自分の子供といえども、価値観や考え方、性格特性は異なっており、自分の経験に基づいてアドバイスやアプローチをしてもうまくいかないことが多々あります。
そのためには、子育てに関する知識をインプットするとともに、それに基づいて、たくさんの試行錯誤することが重要だと考えています。
自分の経験に基づいた独りよがりな子育てではなく、様々な研究結果や実験を踏まえた合理性の高いアプローチ方法をたくさん知っていることで、子供に対して良い教育ができる可能性が飛躍的に高まります。そういった意味では、今後も最新論文の研究には目を通していきたいと考えています。
あとは、子供の判断、子供の決断、子供の行動にしっかり理解を示して、寄り添ってあげること。これが大事だと思っています。これは口で言うのは簡単ですが、実際に行動するのは本当に難しいです。
日々の子育てにおいて、自分への戒めも含めて、しっかりと肝に銘じたいと思います。

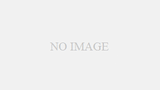

コメント