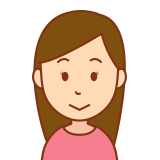
最近、「非認知能力」という言葉をよく聞くけど、どういう能力なのかしら?
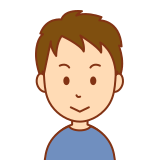
今、世界的に注目されているね。生涯を通した学びの姿勢や生活の質を高める能力と言われているよ。
非認知能力とは?
今、世界の教育トレンドの1つとなっている「非認知能力」。
その非認知能力とは、
意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力
などを指すことが多いです。
いわゆる「お勉強ができる能力」「国語・算数・理科・社会ができる能力」などの学力は、「認知能力」といわれます。「認知能力ではない能力」ということで非認知能力と呼ばれます。
非認知能力は、なぜ重要なのか?
非認知能力の重要性がさけばれるようになった背景には、2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームス・ヘックマン(James Heckman)の研究結果があります。
具体的には、以下の2つのプロジェクトから、幼児期において非認知能力を教育された子どもたちは、その後の人生において、学力検査の成績がよく、学歴が高く、収入が多く、生活保護受給率や逮捕者率が低かったという結果がでています。
- ペリー就学前プロジェクト
- アべセダリアンプロジェクト
この研究結果を受けて、世界中で幼児期における非認知能力の教育がトレンドとなりました。
実は、非認知能力はあまり解明されていない
教育トレンドとなった非認知能力に関する研究が増えていきますが、実は、非認知能力の解明はあまり進んでいない印象です。
もう少し詳しく言うと、
非認知能力の概念が抽象的で、人や組織によって解釈の幅が広い
と言える状況です。
もっと言うと、非認知能力の獲得方法については、現在進行形で研究が進んでおり、効果的な獲得方法は確立されてきていない状況です。
非認知能力とは何か? 【さまざまな定義】
先述の通り、非認知能力といっても、とても幅広い特性が含まれます。
やる気、自信、粘り強さ、信頼感、忍耐力、社会性やコミュニケーション能力などです。
後ほど、紹介しますが、日本の文部科学省では、心理学で古くから研究対象であった「社会的情緒的能力」と読んだります。
つまり、細かく丁寧に見ていくと、人や組織において、どのように非認知能力を定義するかは、異なります。
非認知能力とは? 【文部科学省の定義】
まずは、日本の教育行政を担う文部科学省による定義を見てみましょう。
非認知能力とは? 【OECDの定義】
次に世界のシンクタンクと呼ばれるOECD()による定義を見てみます。
正直、非常に難解ですが、丁寧に読み解く価値は十分にあります。
非認知能力とは? 【Institute of Education(ロンドン)の定義】
教育に関する世界最高峰の研究機関であるイギリスのInstitute of Educationによる定義を見てみます。
- セルフパーセプション
- モチベーション
- 忍耐力
- セルフ・コントロール
- メタ認知戦略
- ソーシャルコンピテンシー
- レジリエンスとコーピング
- 創造性



コメント