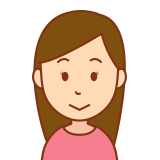
親はあまり子どもに介入しない方が良いって聞くけど、子どものことも心配だし……
どのような親子関係の距離感が良いんだろう?

ある研究で、学校での子どもの成績と、親の関与程度を研究したところ、「親が関与した方が子どもの成績は良くなる」ということがわかった。
では、どのように子どもに関わっていけばよいのか?
その介入の考え方がとても重要なんです。
今回は、「学校での子どもの成績」と「親の子どもへの関与」の関係性について、紹介します。
子どもの成績は、親の社会経済的地位に大きく関連する
- 親の年収が子供の成績に大きく影響する。
- 東大生の親の平均年収は1,000万円。
このようなことを一度は、聞いたことがあると思います。 ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この主張は、さまざまな研究から正しいとされています。家族の社会経済的地位と子どもの学業成績との関連性を示す証拠は「圧倒的」と言われています。
では、所得が低いと感じている家庭は、この事実をどのように受け止めるでしょうか?
年収が低い自分(=親)の子供は、将来の成績は悪いことが決まりきっているのか。
と思いますよね?
そう簡単に収入を上げることは難しいですし、社会経済的地位は周りからの信頼や承認が必要で、一長一短に獲得できるものではありません。
子どもの成績に影響を与えているのは、親の経済力だけなのか?
一方で、こんな疑問も頭に浮かびます。
- 親の年収・経済面だけが、子供の成績、教育に影響しているのか?
- 親の年収・経済面が、子供の成績に最も影響を与えているのか?
重要な問いですね。実は、答えは、NOです。
ある研究では、子供の成績に最も影響を与える要件、つまり、子供の教育に大きく影響を与えているものは、親の介入(=行動)だとわかっています。
それでは、家族の社会経済的地位が高ければ、親は積極的に子供の教育に介入していくのでしょうか?
実は、それもNOです。
親の介入(行動)は、「教育に対する親の価値観、子どもの学校生活への関与や希望、子どもの学校での成功への関心、子どもの達成感への願望」が大きく影響します。
つまり、総合的に考えると、子供の学校での教育の成果は、社会経済的地位の違いを超えて、親が何を考え、何をするかが大きく影響します。親の社会経済的地位ではありません。
親は何を考えるべきなのか?
それでは、親はいったい何を考えればよいのか?
それは、「親の役割とは何か?」ということです。
抽象的な問いですが、この問いについて、しっかりと考え抜き、自分なりの答えを持つかどうかで、親の行動が変わっくるというのです。
「親の役割」が構築されることは、子どもへの関与のプロセスにおいて重要であると考えられています。
親が、子どもとの間、あるいは子どものために行動する際に、「親(=自分自身)が子どもにとって重要で、必要で、許される存在」と考えられることが重要です。
学校での成績が良い子どもの親は、「教育において、親ができることは何か?」ということを考え得ているといいます。逆に、学校の成績が悪い子どもの親は、「教育は先生がするもの」と考えています。「教育において、親の存在が重要で、必要で、許される存在」という考えがないわけです。
親がどのような考えを持つと、子どもはどのように育つのか?
親の考え方、特に「親の役割」に対する考え方が、子どもの成績に大きな影響があることがわかったと思います。
それでは、具体的に、「親がどのような考えを持つと、子どもはどのように育つのか?」を見ていきたいと思います。
- 親が、子どもに従順さや良い行動を身につけさせることが重要であると考えると、子どもは学校での成績が悪い。
- 親が、子どもに個人の責任と自尊心を身につけることが重要であると考えると、子どもは学校での成績が良い
- 小学校低学年では、親が順応性、清楚さ、良いマナー、良い行動を重んじると、子どもの言語、読解、算数の達成度の低下、全体的な知的パフォーマンスの低下、教室での行動の低下、自信の低下を招く。
- 小学校高学年の子どもでは、子どもが礼儀正しく行動することを親が強く支持することは、認知能力の低下、自尊心の低下、行動障害の発生率の上昇、学校での引きこもりの増加と関連がある。
- 子どもは受動的に学ぶものだという親の信念は、子どもの達成度の低下、教室での行動の低下、課題志向の低下と関連がある。
- 子どもの学業成績の向上は、自立的思考、個人的責任、子どもの自尊心の育成を重視する親の信念と関連する。
いかがでしょうか。
皆さんの周りの親子、あるいはご自身が当てはまるものもあるかもしれません。
親が家庭教育・家庭支援の中で強い信念をもって、子どもに関わるといっても、考える方向性を間違えば逆効果になってしまいます。
まとめ
いかがだってでしょうか。
子どもの教育における自分の役割について、積極的で能動的な考えを持ち、その考えに基づいて行動している親が、子どもに良い影響を与えることが理解していただけたのではないでしょうか。
これから、論文からさまざまな研究を参考に、子育て・幼児教育・人材育成に関するさまざまな情報を発信していきます。



コメント