教育ビジネスの特殊性
塾や家庭教師、その他の教育サービスにも当てはまることが多いですが、子ども向け教育ビジネスには「ある特殊性」があります。
それは、「お金を支払う人」と「サービスを受ける人」が異なるということです。その他の一般消費者向けビジネスの多くは、「お金を支払う人」と「サービスを受ける人」が同じです。
飲食店では、お金を払った人が飲食でき、衣料品店では、お金を払った人が衣服を手に入れられます。
一方、子ども向け教育ビジネスでは、お金を払うのは親で、教育サービスを受けるのは子どもです。一般的な消費者向けビジネスとは大きく異なります。
教育という分野は、「教師は全体の奉仕者である」と明記されているため、教育者が大儲けをしている姿は理想的ではないと考えられうかもしれません。しかし、教育ビジネスは、資本主義の中における、れっきとしたビジネスであり、その会社を経営する人が利益を追求することに、何ら問題はありません。
ただ、利益を追求するビジネスの世界では、教育の本質が二の次にされがちだったり、「短期的な、目先の、わかりやすい成長」だけを重視されたりします。
本当に大事なこと、教育の本質のようなものは、わかりにくかったり、即効性がなかったりするので、なかなか「商品」として理解されづらかったりします。
お金を支払う人である親は、この教育ビジネスの特殊性をしっかり把握した上で、自分の子供に教育を提供するべきだと考えます。
子育てで重要なのは、自己決定の機会
人間の幸福感には、「自己決定の機会がどれだけあるか」が大きく影響することが分かっています。
それを子育てにも応用すると、子育ての中でも自己決定の機会をたくさん盛り込むことが重要です。
服を選んだり、読みたい本を選んだり、遊びたいおもちゃを選んだり、遊びたい公園を選んだり、何でもいいので、子ども自身が「自分で決定する」ということを習慣づけることが大事です。
それを踏まえた上で、教育サービス、例えば習い事で塾に通う場合、子供が自分で選択するということが非常に重要です。親が、一方的に、「これを学ばせたい」、「この塾がいい」、「この学校がいい」など、子供が選ぶのではなく、親が決めたことに子供を従わせるということが少なくありません。そのような考え方は、子どもにとって望ましくありません。
このような考え方をする親は、どちらかというと、教育熱心な親で、むしろ自分の教育方法は非常に素晴らしい、子供ためを思って良いことをやっている、と思いがちです。
この考え方は、本当に危険です。
皆さんも経験があると思いますが、子供の頃まで従順で素直だったから親の言うことにも従っていたけど、だんだん大きくなっていくにつれ、自分のやりたいことや好きなことが明確になってくると、なんでいちいちそんなこと決めてくるんだよ、ほっといてくれよ!自分でやるからもういいよ!という風に思って、親の介入が鬱陶しく感じた経験があるのではないでしょうか。
親が子育てに介入することは良いことですが、介入の仕方が問題です。1から10まで、全て親が決めて、それを子供にやらせるのではなく、子供が右に進めたいと思っている時に、道を進む中で障害物があったら取り除いてあげる、背中押してあげる。こういった介入の仕方が本来の教育子育てという考え方だと思います。
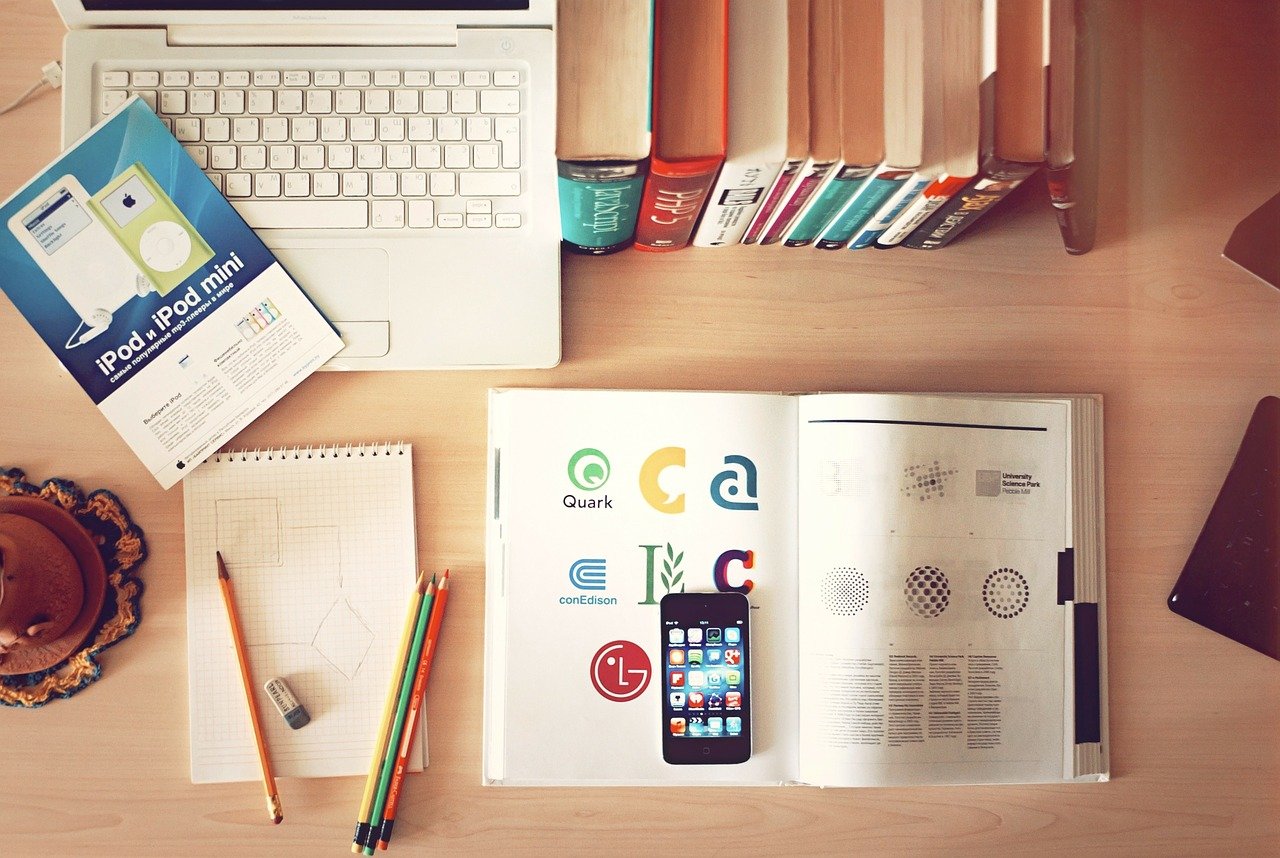
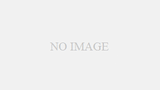

コメント