実は、昨年の秋頃から、我が子がSAPIX(サピックス)に通い始めることになりました。正直なところ、この決断に至るまで、いろいろと悩みと期待が入り混じった中で迷ってきた、、というのが本音です。
この記事では、同じように「SAPIXどうしようかな」「新4年生から通わせるのってどうなんだろう」と悩んでいる親御さんに向けて、我が家がSAPIXを選んだ経緯や、いま感じているリアルな気持ちを、飾らずにお伝えできればと思っています。
なぜSAPIXを選んだのか:我が家の迷いと決断
中学受験という言葉が、少しずつ現実味を帯びてきたのは、我が子が小学3年生の後半に差しかかった頃でした。
迫りくる「新4年生の壁」と中学受験
周囲の友人や同僚の話を聞いていると、どうやら本格的な中学受験の準備は小学3年生の2月、つまり「新4年生」からスタートするケースが多いとのこと。のんびりしていた我が家も、さすがに「そろそろ考えないといけないのかな」と、妻と顔を見合わせるようになりました。
息子自身は、特に勉強が嫌いというわけではありませんが、遊ぶのが大好きなごく普通の小学生です。そんな息子に、本当に中学受験という道が合っているのか、それ自体も悩みのひとつでした。
SAPIXという選択肢:輝かしい実績と厳しい評判
塾選びを始めるにあたり、やはりSAPIX(サピックス)の名前は真っ先に挙がりました。圧倒的な合格実績は誰もが知るところですし、質の高い授業を提供しているという評判もよく耳にします。
一方で、「SAPIXはとにかく大変」「宿題の量がすごい」「ついていくのが難しい」といった声も、同じくらい聞こえてきました。正直、その厳しそうなイメージに、最初は少し尻込みしていた部分もあります。
正直なところ、迷いました:他の塾や本人の気持ち
もちろん、他の大手進学塾や、もう少し小規模で面倒見の良い塾も検討しました。それぞれの塾に説明会に足を運び、資料を見比べ、体験授業にも参加させてみました。
どの塾にも魅力的な点があり、正直、かなり迷いました。「SAPIXでなくても、息子に合う塾があるのではないか」「もっと本人のペースを大事にしてくれるところの方が良いのではないか」と、何度も考えました。
息子本人にも、それぞれの塾の印象を聞いてみましたが、まだ小学3年生の彼には、塾ごとの明確な違いや、将来の目標といった具体的なイメージは湧きにくいようでした。「どこでもいいよ」と言うこともあれば、「あそこの先生は面白かった」と言うこともあり、親としては判断材料をどこに置くべきか悩ましかったです。
最終的にSAPIXに決めた理由
最終的にSAPIXに決めたのは、いくつかの理由が重なった結果です。
ひとつは、やはりその環境です。高い目標を持つ多くの仲間たちと切磋琢磨できる環境は、息子の負けず嫌いな性格を良い方向に刺激してくれるかもしれない、と考えました。
また、質の高い教材と、論理的な思考力を鍛えるというSAPIXの教育方針にも魅力を感じました。たとえ中学受験という結果がどうであれ、そこで培われるであろう学習習慣や思考力は、息子の将来にとって必ずプラスになるはずだ、と。
そして、何よりも大きかったのは、体験授業を受けた後の息子の言葉でした。「なんだか難しかったけど、ちょっと面白かった」と、少し目が輝いていたのです。その小さな変化を見て、大変かもしれないけれど、一度挑戦させてみる価値はあるのかもしれない、と妻とも話し合い、決断しました。
SAPIX通塾開始へ:期待と不安が入り混じる日々
入室テストも無事に(?)終わり、いよいよ通塾が目前に迫ってきました。今は、期待と不安が本当に複雑に絡み合っている状態です。
入室テストとクラス分け:最初の関門
入室テストの結果でクラスが決まると聞き、親としてはやはり少しドキドキしました。幸い、本人はそれほどプレッシャーを感じていなかったようですが、これから始まる「競争」の入り口に立ったような気がして、私が緊張してしまいました。
教材の量と宿題:噂は本当なのか
SAPIXといえば、その教材の量と宿題の大変さがよく語られます。実際に教材見本を見せてもらうと、確かに噂通り、かなりのボリュームです。これを毎週こなしていくのかと思うと、親子共々、相当な覚悟が必要だと感じています。
平日は学校の宿題や習い事もあり、週末もどこまで時間が取れるのか。親として、どのようにサポートしていけば良いのか、今からシミュレーションを繰り返す毎日です。
授業のスピードと内容:子供はついていけるのか
授業のスピードが速く、内容も高度だと聞きます。息子があのスピード感についていけるのか、授業で分からなかったことをそのままにしてしまわないか、という点は大きな不安要素です。
先生方はプロなので、子供たちの理解度をしっかり把握しながら進めてくれるとは思いますが、家庭での復習がどれだけ重要になるのか、身をもって感じることになりそうです。
親としてのサポート:どこまで関わるべきか
SAPIXに通うとなると、親のサポートが不可欠だと言われます。スケジュール管理、宿題の進捗確認、教材の整理、そして何よりも精神的なサポート。どこまで親が介入すべきなのか、過保護になってもいけないし、かといって突き放すのも違う。そのバランスをどう取っていくのかが、これからの大きな課題だと感じています。
仕事との両立も含め、親自身の生活も大きく変わることになるでしょう。それだけの覚悟を持って、親子で一緒に乗り越えていく必要があるのだと、改めて気を引き締めています。
これからSAPIXを考える皆さんへ:同じ親としての気持ち
まだ通い始めてもいない我が家が偉そうなことを言える立場ではありませんが、同じようにSAPIXを検討されている親御さんに、今の時点で感じていることを少しだけ共有させてください。
情報収集の大切さと、家庭ごとの判断
SAPIXに関する情報は、インターネット上にもたくさんあります。良い評判もあれば、厳しい意見もあります。できるだけ多くの情報を集めることは大切だと思いますが、最終的には、それぞれの家庭の教育方針や、お子さんの性格、そして家庭環境などを総合的に考えて判断することが重要だと感じています。
我が家も、本当に多くの情報に触れましたが、最後は「我が子にとってどうか」という視点で考えるようにしました。
子供の意思を尊重すること
いくら親が熱心でも、最終的に学ぶのは子供自身です。もちろん、まだ幼い子供に全ての判断を委ねるわけにはいきませんが、子供がどう感じているのか、何に興味を持っているのか、その声に耳を傾けることはとても大切だと思います。
我が家の場合も、息子の「ちょっと面白かった」という言葉が、最後の決め手の一つになりました。
親も一緒に成長する覚悟(のようなもの)
中学受験は、子供だけでなく親にとっても大きな挑戦だと聞きます。これから始まるSAPIXでの日々は、きっと大変なことも多いでしょう。でも、子供が頑張る姿を一番近くで応援し、一緒に悩み、一緒に喜ぶことができる貴重な時間になるのかもしれない、とも感じています。
親自身も、子供と一緒に学び、成長していく。そんな気持ちで、この新しいスタートを切りたいと思っています。
まとめ:不安と期待を胸に、親子で踏み出す一歩
SAPIX(サピックス)への通塾を決めた我が家の、通い始めを控えた今の率直な気持ちをお伝えしました。不安は尽きませんが、それ以上に、息子が新しい環境でどんな学びを得て、どんな成長を見せてくれるのか、という期待も確かにあります。
これから、親子で力を合わせて、一歩ずつ進んでいければと思っています。このブログが、少しでも同じような状況の親御さんの参考になれば、そして共感していただける部分があれば、とてもうれしいです。
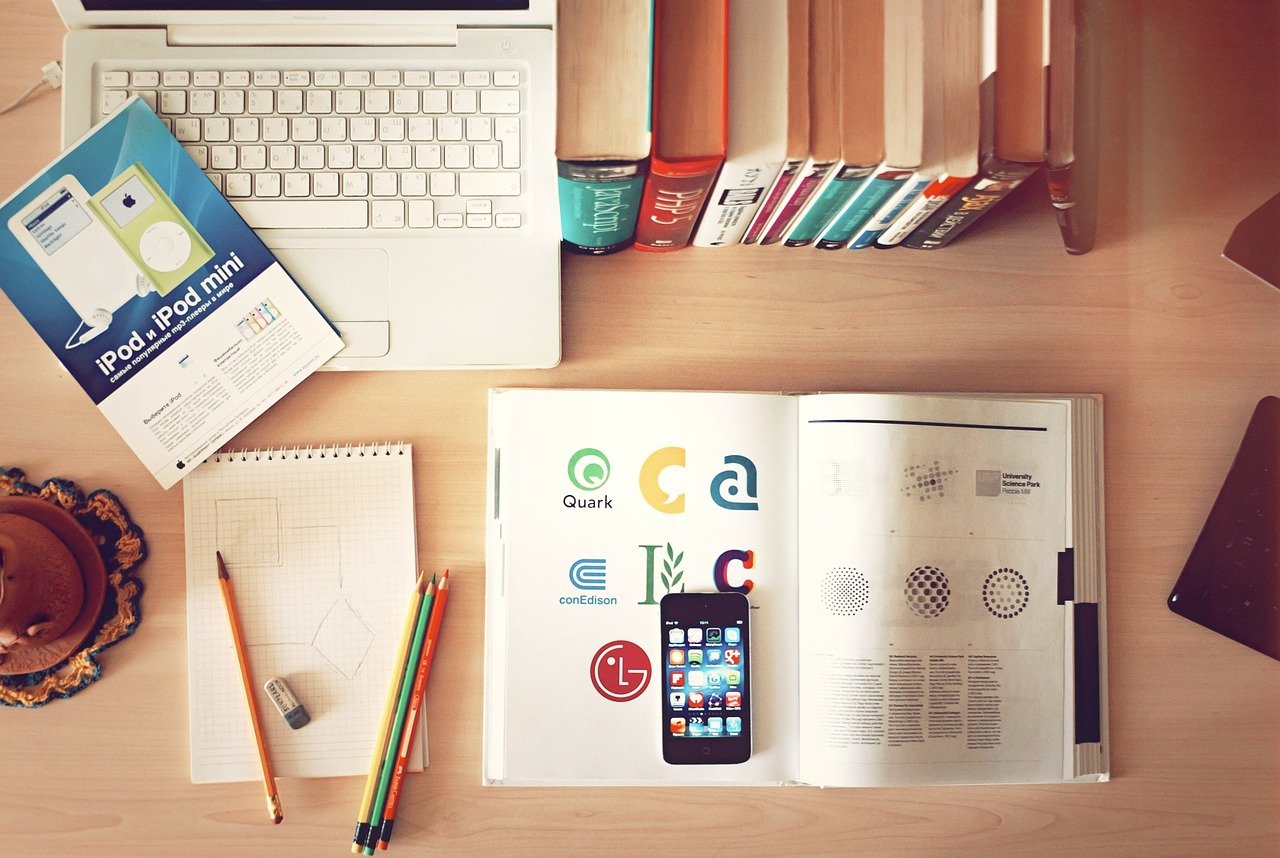


コメント